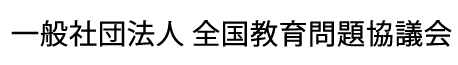教科書法案の提出、早急な課題に
2月27日、日本の教育正常化をめざす一般社団法人・全国教育問題協議会(中尾建三理事長)は第三回役員会を東京都千代田区永田町で開き、これまでの活動報告や今後の方針などについて来賓や顧問の方々の意見を取り入れながら多方面に活発な意見交換を行いました。
来賓として上野通子(うえのみちこ)参議院議員(自民党文部科学部会副部会長)や宮崎貞行議員立法支援センター代表、全教協顧問の小林正氏(教育評論家、元参議院議員)、杉原誠四郎・武蔵野女子大学元教授(新しい歴史教科書をつくる会前会長)、友好団体である全日本教職員連盟の岩野伸哉委員長(日本教育文化研究所長)が今後の日本の教育のあり方について、それぞれの立場から報告されました。
とくに深刻な教科書会社の不正や教科書検定のあり方の問題点を改善するために必要な教科書法案(教科用図書基本法)の制定は重要で、立法化に向けてしっかりとした準備をしていく国民的な議論へ展開できるようにしていくように決議。
歴史教育で聖徳太子の名前をあえて消していこうとする亡国左翼史観、日教組の動きに対しては警鐘を鳴らす必要があることを共通認識しました。詳細については追って紹介します。以下、会議の写真をアップします。
【できるだけ早期に教科書法案を提案する理由】
一般社団法人「全国教育問題協議会」は平成29年2月27日の第三回役員会でできるだけ早急に教科書法案の制定が必要であることを決議しました。全国教育問題協議会が教科書検定のさまざまな問題点を改革、刷新させるために教科書法案を立法化推進が必要不可欠であるとの理由は以下の通りです。
■教科書行政法の一本化
平成18年12月改正教育基本法が公布・施行されたが、旧来の教育基本法が制定されて今日まで部分改正を繰り返してきた教科書行政法を一まとめに一本化する必要があります。
■総合的な教科書行政に必要な教科書法案が廃案になったままの現状刷新
「教科書発行に関する臨時措置法」は戦後間もない昭和23年、経済の混乱、教科書用紙の不足という困窮事態に対処するための臨時措置として定められた法律で、当時と現状は大きく違うのに変わっていない。昭和31年、総合的な教科書行政のための「教科書法案」成立が図られましたが、参議院で廃案となり、現状に至っていますので、総合的な法案を立法化する必要不可欠な時期になっています。
■教科書検定規則の新たな明文化は教科書の調査・審議の透明性を確保するために必要かつ重要
教科書検定制度は本来、教科書が学習指導要領に準拠して作成されているかどうかを基準として進められてきました。昭和38年、「義務教育諸学校の教科書図書の無償措置に関する法律」が成立し、教科書の無償給付や給与措置が取られ、あわせて教科書の採択、発行が法文化されました。また、昭和33年、従来の試案だった学習指導要領が基準となって、文部大臣の公示、官報に告示されるようになり、法的拘束力を持つようになりました。教科書検定規則はこれまで省令に委ねられてきましたが、法律事項に格上げ、明文化することで検定基準とともに、教科書の調査・審議の透明性を確保する上できわめて重要な核心部分となります。
■教育委員会の職務権限と教科書採択制度の間にある矛盾解消
平成23年、中学校教科書採択をめぐっては「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が定める教育委員会の職務権限と「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の広域採択制度との間に深刻かつ重大な矛盾を来しています。これらの事態を解決・解消し、「弥縫(びほう=失敗や欠点を一時的にとりつくろうだけの状態)的だ」と指摘・批判されている教科書行政を総合的な教科書法案として抜本的に改正・整備することが必要不可欠であり、急務です。
以上が一般社団法人・全国教育問題協議会が提案する教科書法案の策定理由です。
平成29年2月27日 一般社団法人 全国教育問題協議会 第三回役員会