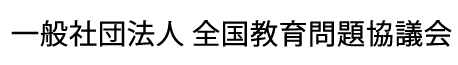教育委員会とはどんな組織なのか
◆教育委員長と教育長
子供の小学校の卒業式に出席したら、教育委員長が来賓として来ていました。上の子の時は、確か教育長でした。教育委員長と教育長は、いったいどう違うのか。早い話、どちらがえらいのか。そんな疑問を持った人は少なくないでしょう。現在の教育委員会制度は、複雑で分かりにくい。このところ、いじめが原因と見られる自殺が相次いでいますが、教育委員会が迅速に対応できないケースが続いていることから、今、制度をどう改革したらいいのか、専門家たちが話し合っています。
教育委員会は、知事や市長などの首長から独立した行政委員会です。通常5人の教育委員が、月に1、2回、会合を開き、教育方針などを話し合って決めます。教育委員会には、自治体の職員であるスタッフがいる事務局があり、教育委員会の決定に基づいて教育事務を執行します。事務局の責任者を「教育長」と呼び、教育委員の一人が兼任します。
◆最初は絶大な権限
そもそも、教育委員会制度は、第2次世界大戦後、教育があまり政治に影響されないようにと、アメリカの意向で、アメリカの制度にならって作られたものでした。1948年に「教育委員会法」が制定されましたが、その基本は民意の尊重と地方分権です。地域住民の常識的な判断により、政治的な中立性を確保し、教育政策が継続・安定して行われることが期待されました。教育委員は選挙で選ばれ、しかも教育の予算案提出権を持っていました。スタート当初は権限も責任も絶大だったのです。
当時、教育委員会には素人ならではの判断、教育長が率いる事務局には教育のプロとしての役割を期待されていました。実際、教育長は校長と同様に免許制だったのです。
1952年、都道府県だけでなくすべての市町村にも設置が義務付けられましたが、当時、市町村は1万近くあり、そのすべてに教育委員や教育長にふさわしい人材を見つけるのは困難でした。そこで、苦肉の策として、市町村に限っては、教育委員が教育長を兼任できるようにしたのです。
とはいえ、指揮監督する立場にある教育委員が、指揮監督される事務局の責任者を兼ねるのは不自然です。そこで、市町村も都道府県にあわせて、専任の教育長をおくべきだとの声が高まり、文部大臣の諮問機関である中央教育審議会がそのような答申を出したのですが、特別職を増やすのは行政改革に逆行するという反対意見の方が強く、答申とは逆に都道府県でも教育長は教育委員が兼任するようになったのです。
もうひとつの流れが、地方行政の中での位置づけをめぐるものです。
1950年代中頃までは、教育委員会が議会に教育予算案を提出したため、混乱を招くことも少なくありませんでした。本家のアメリカと違い、首長選に落選した候補が、教育委員選挙に立候補して選ばれることも多く、本質的に首長と対立する構造になっていたのです。このため、1956年の制度改正で、予算の提出権と公選制が廃止されるなど、教育委員会の力はどんどん削られていきました。首長の意向に沿って動く委員が選任され、議論が形骸化したのも、こうした流れの中では必然だったのかも知れません。
◆委員の人選がカギ
今日、教育委員会には、制度導入時とは逆に、教育の専門知識を持っていることが期待されているようです。これに対して、事務局は一般の行政職員が務め、教育長も県庁や市役所の元職員ということが多いようです。つまり、教育のプロ集団である委員会が、素人集団である事務局を指揮監督する構図です。
都道府県レベル、市区町村レベルなど様々な教育委員会の会合を傍聴しましたが、委員による鋭い指摘が政策の改善につながっている例がある一方、おざなりな議論で終わっているところもありました。教育委員は、知事や市長が議会の同意を得て任命しますが、しかるべき人物が選ばれ、きちんと議論して意見を述べるのであれば、今の制度でも十分存在意義を示すことができるのです。その意味で、教育委員会改革で最も重要なのは、人選の方法の見直しということができるでしょう。
(2013年7月18日 読売新聞)